道真公のことを知りたくて、手にとった一冊。どんどん読み進めてしまうような面白い作品だった。時平を主人公にすえるという面白い試みで、そういう見方もあるかぁと唸らされる内容だった。

時平と道真は、立場が異なれば親友にもなりえたのかもしれない。「アマデウス」という映画を思い出した。「アマデウス」では、モーツァルトではなく、ライバルであるサリエリを主人公として描く。そのサリエリだけが、モーツァルトの本当の力を知っている。皮肉にも、モーツァルトという人のことを真に理解しているのは、ライバルであるサリエリだけである。
外野から見れば、もっとも相手のことを嫌っているだろうというライバル本人だけが、相手という人間をもっともよく理解している。道真のことを本当に理解していて、一番高く評価していたのは、時平だったろう。
最後のシーンで、時平が道真の左遷を決定した後、弟である忠平が、「道真と宇田上皇は別に何もしようとしていなかったことに時平も気づいていたはずだ」という。これは、この作品において重要なセリフだったと思う。歴史的には、時平のあとをつぐことになる忠平は、本作では時平の内心を見抜いているかのような振る舞いをする。忠平に、作者の代わりを勤めさせた、ということだろう。
時平は、以下のセリフを口にする。
「大陸からもたらされる技術、学問は新しい。日の本が学ぶべきことが多い。されど、朝廷で自国の言葉を使わぬなど、外にばかり目を向ける国家のあり方は、時平にはどうしても諾と頷く気にはなれぬ。進出と言えば聞こえは良いが、異国と同化することで、見失うものもあるのではないか。そう思うのは、能なき己の僻みだろうか。」(引用)
これは、今の世の中にもそのまま当てはまる課題。歴史は繰り返す、とはよく言ったものだ。
西郷南洲遺訓には、次の記述がある。
「広く各国の制度を採り開明に進まんとならば、先ず我が国の本体を据え風教を張り、しかして後しずかに彼の長所を斟酌するものぞ」
欧米各国の制度を採用して日本を開明させるのならば、、それよりも先にしなければならないことがある。まず日本が国の基本をしっかり定めた上で、徳を持ってそれを支えるようにすることである。
道真は、「和魂漢才」という精神を唱えたことでも有名であろうから、むしろこの時平の考えは、道真の考えるところと同じであっただろう。最後のシーンで、左遷の決まった道真が、あの有名な「やまとうた」を詠んだという描写がある。この1つのシーンによって、道真の和魂漢才の精神を描写したのかもしれない。
本作において、道真の考えを端的に示す言葉として、「能なき者は去れ」という言葉がある。紀貫之は、道真のことを「俊才ゆえに誤解され易き方だったのかもしれぬ」という。不器用だったということもできるだろう。実際の道真公も、遠からずだったように思う。社会、政治、学問、そして人間の「あるべき姿」を追求し、それを自分にも人にも求める、そのような誠実であり、かつ融通の効かない姿勢が、他の人たちに受け入れられなかったのだろうと思う。
時平は、道真公のことを誰よりも恐れ、誰よりも尊敬し、誰よりも理解した男だったのかもしれない。
歴史にifはないけれど、時平と道真が、個人と個人として出会うことができたなら、どんな関係になったのだろう。
また、道真が政治家ではなく、貫之のような歌詠みとして生涯を全うしていたら、あるいは、学者として全うしていたらどうだったのだろう。
そんなことを考えてみたくなる。

- 作者: 奥山景布子
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2014/03/20
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログを見る




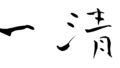
コメント